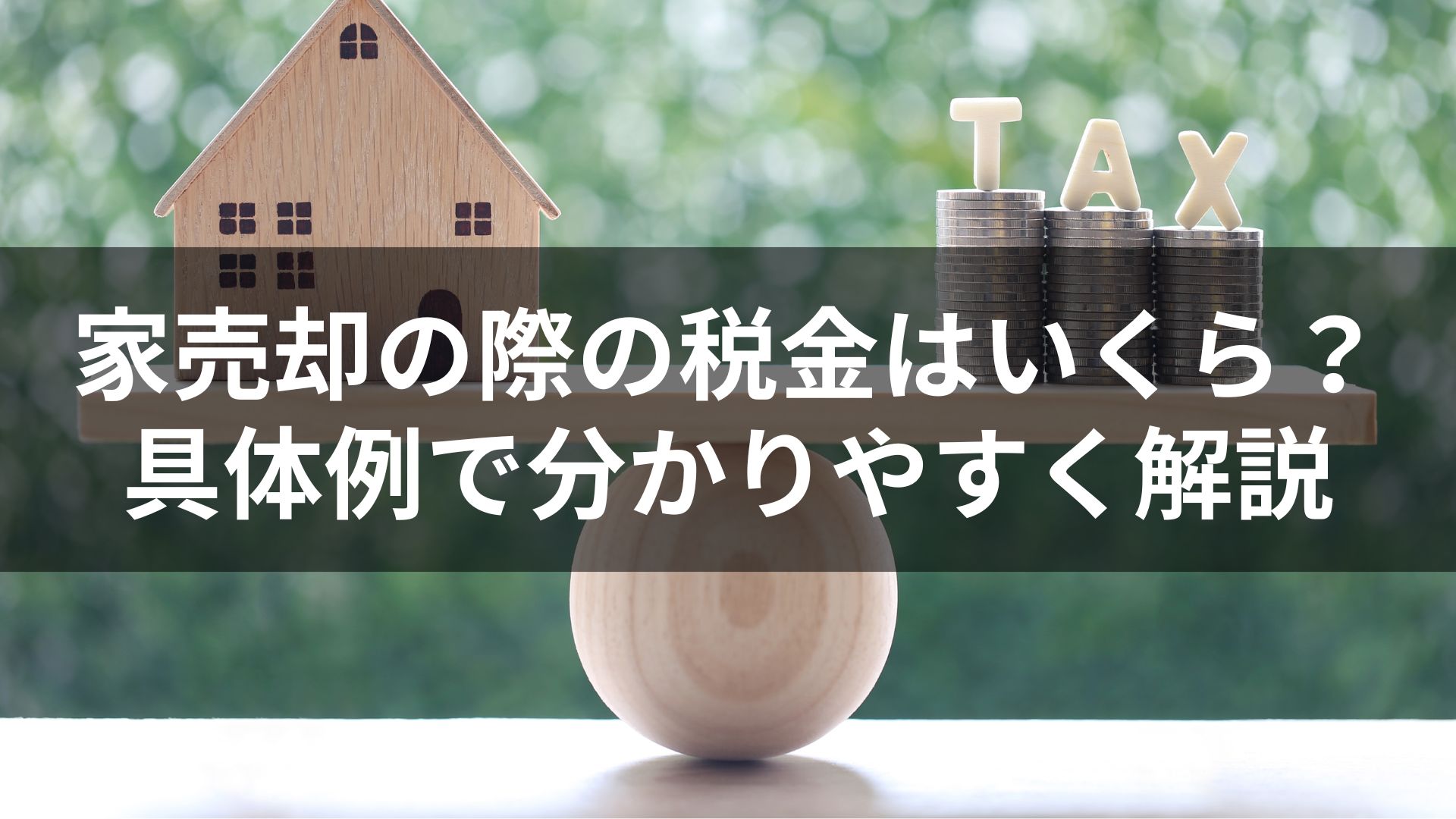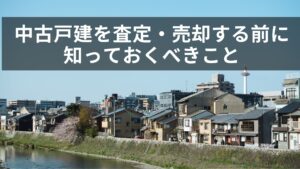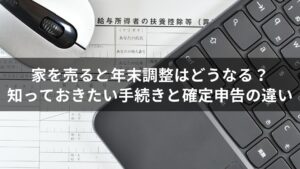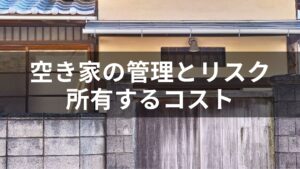家を売却する際にかかる税金を知っておくことは非常に大切です。不動産売却に関する税金は複雑で、知らないと損をしてしまうこともあるでしょう。
所有期間や売却価格によって税率が変わる譲渡所得税、特例や控除を使った節税対策、正確な税金計算の方法など、抑えるべきポイントはたくさんあります。
このコラムでは、家売却時にかかる税金の種類や計算方法、そして効果的な節税対策について丁寧に解説します。これを読んで、賢く家を売却し、無駄な税負担を避けましょう。
\ 川越・所沢・狭山の不動産売却ならお任せ /
市街化調整区域の土地、相続を受けた遠方の不動産、事故物件、再建不可の建物など、他の不動産会社で買い取り不可と判断された不動産でも、弊社であれば買い取り可能な場合もあります。是非お問い合わせください!
家売却時にかかる税金とは?

家売却時に必ずかかる税金
- 印紙税
- 登録免許税
売却時に必ずかかる税金には、印紙税と登録免許税があります。印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙代で、契約書の記載金額によって税額が異なります。
例えば、売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円です。契約書の原本には必ず印紙を貼り、消印をする必要があります。登録免許税は、所有権移転登記の際にかかる税金で、土地や建物の価額に一定の税率を乗じて計算されます。通常、この税金は引渡しの際に支払われます。
家売却時に場合によってかかる税金
- 譲渡所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
売却価格が取得価格を上回り、利益が出た場合には、譲渡所得税が発生します。この税金には、所得税、住民税、復興特別所得税が含まれます。譲渡所得税の税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期所有の場合は39%、5年超の長期所有の場合は20%です。
譲渡所得税の計算には、取得費や譲渡費用を正確に把握することが重要です。また、復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%が追加で課税されます。
税金がかからないケース
- 利益が発生しなかった場合
- 特例や控除を活用した場合
売却により利益が発生しなかった場合や、特例や控除を活用した場合、税金がかからないことがあります。
例えば、3,000万円の特別控除を利用すれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はかかりません。また、譲渡損失が発生した場合には、損益通算や繰越控除を利用することで税金をゼロにすることも可能です。
税金の支払いタイミング
税金の支払いタイミングは異なります。印紙税は売買契約時に、登録免許税は引き渡し時に支払います。譲渡所得税に含まれる所得税は、売却翌年の確定申告期間中(2月から3月)に支払います。住民税については、売却翌年の6月以降に納付書が送付され、それに基づき支払います。
- 印紙税は売買契約時に支払い
- 登録免許税は引き渡し時に支払い
- 譲渡所得税は翌年の確定申告時に支払い
これらの支払い時期をしっかり把握しておくことが大切です。
確定申告の必要性
不動産を売却した場合、必ず確定申告が必要になります。利益が出た場合はもちろん、譲渡損失が出た場合も確定申告を行うことで節税が可能です。
確定申告をすることで、譲渡所得税の正しい額を計算し、必要な特例や控除を適用することができます。確定申告の期間は売却翌年の2月16日から3月15日までですので、余裕を持って準備を進めましょう。
税金の基本を押さえる重要性
不動産売却にかかる税金の基本を押さえることは、売却を成功させるための第一歩です。正しい知識を持っていることで、適切な節税対策を講じ、無駄な出費を抑えることができます。
売却前には必ず専門家に相談し、自分のケースに最適な対策を確認することをお勧めします。適切な準備を行い、税金の負担を軽減しながら、安心して不動産売却を進めていきましょう。
\ 税金ガイドBOOKプレゼント中 /

不動産にまつわる税金のことが一目で分かりやすく説明されている全110ページのガイドブックです(公益社団法人 埼玉県宅地建物取引協会発行)。弊社で無料査定して頂いて、売却されることが決まったお客様全員にプレゼントしています!
譲渡所得税の詳細と計算方法


譲渡所得税について詳しく解説していこう!
譲渡所得税とは?
譲渡所得税とは
- 不動産売却時の利益に課される税金
- 所得税、住民税、復興特別所得税が含まれる
譲渡所得税とは、不動産を売却して利益が出た場合に課される税金です。
この税金には所得税、住民税、復興特別所得税が含まれます。譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額(譲渡所得)に対して課されます。譲渡所得税を正しく計算するためには、売却価格、取得費、譲渡費用を正確に把握することが重要です。
税率と所有期間の関係
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):20%
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得とされ、税率は39%です。これには所得税30%、住民税9%が含まれます。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされ、税率は20%です。こちらには所得税15%、住民税5%が含まれます。
また、2013年から2037年までの譲渡所得には、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が追加で課税されます。
譲渡所得税の計算例
譲渡所得税の計算方法について具体例を見てみましょう。例えば、売却価格が4,000万円、取得費が3,000万円、譲渡費用が200万円、所有期間が6年の場合、譲渡所得は以下のように計算されます。
具体的事例
- 売却価格:4,000万円
- 取得費:3,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 所有期間:6年
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得 = 4,000万円 – (3,000万円 + 200万円) = 800万円
この譲渡所得800万円に対して長期譲渡所得の税率20%を適用します。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得税 = 800万円 × 20% = 160万円
したがって、この場合の譲渡所得税は160万円となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いは、不動産の所有期間に基づきます。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以下
- 長期譲渡所得:所有期間が5年超
- 税率:短期譲渡所得は39%、長期譲渡所得は20%
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得とされ、税率は39%(所得税30%、住民税9%)です。一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされ、税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
所有期間の基準は、売却した年の1月1日時点で計算されますので、注意が必要です。長期所有の方が税率が低く、税金負担が軽くなるため、売却のタイミングを考慮することが重要です。
正確な計算で税額を把握する
譲渡所得税を正確に計算することは、売却利益を最大限に活用するために非常に重要です。売却前に必要な情報を収集し、計算方法を理解しておくことで、税額の把握が可能になります。また、専門家の助言を求めることで、最適な節税対策を講じることができます。正確な計算を行い、売却後の資金計画をしっかりと立てることが、成功する不動産取引の鍵となります。
\ 要点まとめ /
譲渡所得税は不動産売却時の利益に課され、所有期間によって税率が異なります。正確な計算と節税対策が重要です。
\ 川越・所沢・狭山の不動産売却ならお任せ /
市街化調整区域の土地、相続を受けた遠方の不動産、事故物件、再建不可の建物など、他の不動産会社で買い取り不可と判断された不動産でも、弊社であれば買い取り可能な場合もあります。是非お問い合わせください!
節税に活用できる特例と控除


3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除は、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はかかりません。利用条件には、居住用財産であることや、売却する年の前年及び前々年に他の特例の適用を受けていないことなどがあります。また、売却相手が親族や特別な関係者でないことも条件です。
譲渡損失の特例
譲渡損失の特例を利用すれば、譲渡損失を他の所得と損益通算でき、さらに控除しきれない損失については翌年以降3年間繰越控除が可能です。
この特例を利用するためには、譲渡した不動産が居住用財産であること、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること、返済期間10年以上の住宅ローンが残っていることなど、一定の条件を満たす必要があります。
空き家にかかる特別控除
空き家にかかる特別控除は、相続により取得した被相続人の居住用家屋を売却した場合、最高3,000万円まで控除できる特例です。
この特例を利用するためには、被相続人が居住していたこと、相続から売却までの期間が3年10ヶ月以内であること、売却価格が1億円以下であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の活用
住宅ローン控除は、住宅ローン残高の1%を所得税から控除できる特例で、最大10年間控除が可能です。
この控除を受けるためには、新たに購入した住宅が居住用であること、ローンの返済期間が10年以上であることなどの条件を満たす必要があります。また、3,000万円の特別控除との併用はできないため、どちらを利用するかは個々の状況に応じて判断する必要があります。
所有期間による軽減税率
所有期間による軽減税率は、所有期間が10年を超える場合に適用される特例で、譲渡所得にかかる税率が軽減されます。
この特例を利用すると、6,000万円以下の部分に対して14%(所得税10%、住民税4%)、6,000万円超の部分に対して20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。この軽減税率は、3,000万円の特別控除との併用が可能です。長期保有をしている場合は、この特例を活用して大幅に税負担を軽減することができます。
特例と控除を活用するポイント
節税を最大限に活用するためには、各特例と控除の条件をしっかり理解し、自分の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。売却前に専門家に相談し、適切な計画を立てることで、無駄な税金を支払うことを避けることができます。
特例や控除の活用は、資産を有効に管理し、将来的な財務計画を立てる上で非常に有益です。正確な情報をもとに、最適な節税対策を講じましょう。
\ 税金ガイドBOOKプレゼント中 /


不動産にまつわる税金のことが一目で分かりやすく説明されている全110ページのガイドブックです(公益社団法人 埼玉県宅地建物取引協会発行)。弊社で無料査定して頂いて、売却されることが決まったお客様全員にプレゼントしています!
家を売る際の税金に関する注意点
税金支払いのタイミング
家を売る際にかかる税金の支払いタイミングは、それぞれ異なります。
それぞれの支払いタイミング
- 印紙税:売買契約時
- 登録免許税:引き渡し時
- 譲渡所得税:翌年の確定申告時
印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙の購入時に支払います。登録免許税は、所有権移転登記の際に発生し、通常は引き渡し時に支払います。譲渡所得税については、売却翌年の確定申告時(2月16日から3月15日)に支払います。また、住民税は確定申告後に送られる納付書に基づいて支払うことになります。
取得費が不明な場合の計算方法
取得費が不明な場合は、概算取得費を使用して計算します。
概算取得費とは、売却価格の5%を取得費とする方法です。例えば、売却価格が3,000万円の場合、取得費は150万円(3,000万円 × 5%)となります。
この方法を使用することで、取得費が不明な場合でも譲渡所得を計算することができます。ただし、実際の取得費がこの概算取得費を上回る場合は、実際の取得費を使用した方が税負担が軽減される可能性があります。
税金以外にかかる費用
家を売る際には税金以外にもさまざまな費用がかかります。代表的なものとして、不動産会社に支払う仲介手数料があります。
仲介手数料は通常、売却価格の3%+6万円+消費税が一般的な計算方法です。その他にも、引越し費用や修繕費用などがかかる場合があります。これらの費用をあらかじめ見積もり、売却後の手取り額を正確に把握しておくことが重要です。
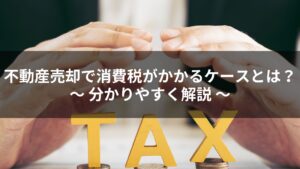
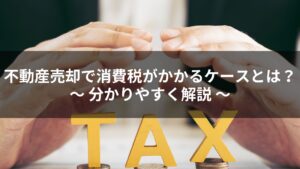
取得費が分かる場合の計算方法
取得費が分かる場合は、実際の取得費用を使用して計算します。
取得費用には、不動産の購入価格、購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税などが含まれます。譲渡費用として、不動産の売却にかかった費用(仲介手数料、修繕費用など)も差し引きます。
これにより、正確な譲渡所得が計算されます。例えば、取得費が3,000万円、譲渡費用が200万円、売却価格が4,000万円の場合、譲渡所得は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得 = 4,000万円 – (3,000万円 + 200万円) = 800万円
税金計算の際の注意点
税金計算の際には、正確な情報を基に計算することが重要です。取得費や譲渡費用をしっかり把握し、必要な書類を準備しておくことで、正しい譲渡所得を計算することができます。また、税務に詳しい専門家に相談することで、適切な節税対策を講じることが可能です。特に、不動産売却は大きな取引ですので、計算ミスや見落としがないように注意しましょう。
\ 川越・所沢・狭山の不動産売却ならお任せ /
市街化調整区域の土地、相続を受けた遠方の不動産、事故物件、再建不可の建物など、他の不動産会社で買い取り不可と判断された不動産でも、弊社であれば買い取り可能な場合もあります。是非お問い合わせください!
税金対策の具体例とシミュレーション



具体例とシミュレーションで見てみよう!
所有期間5年以下のケース
- 短期譲渡所得として扱われる
- 税率は39%(所得税30%、住民税9%)
- 節税対策が限られる
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として扱われ、税率は39%となります。これは、所得税30%、住民税9%を含みます。短期間での売却は税率が高く、節税対策が限られるため、売却時期を慎重に検討することが重要です。
所有期間5年以上のケース
- 長期譲渡所得として扱われる
- 税率は20%(所得税15%、住民税5%)
- 3,000万円の特別控除が適用可能
所有期間が5年以上の場合、長期譲渡所得として扱われ、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。所有期間が長いほど税率が低くなり、節税効果が期待できます。また、3,000万円の特別控除が適用可能であり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金は発生しません。
所有期間10年以上のケース
- 軽減税率が適用される
- 6,000万円以下の部分は14%、6,000万円超は20%の税率
- 3,000万円の特別控除との併用が可能
所有期間が10年以上の場合、さらに税率が軽減されます。6,000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)、6,000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。3,000万円の特別控除との併用も可能であり、譲渡所得に対する税負担を大幅に軽減することができます。
特例を使った節税シミュレーション
特例を使った節税シミュレーションでは、以下の例を考えてみましょう。
売却価格が5,000万円、取得費が2,500万円、譲渡費用が500万円の場合、譲渡所得は2,000万円(5,000万円 – 2,500万円 – 500万円)となります。この譲渡所得から3,000万円の特別控除を適用すると、課税所得はゼロになり、税金は発生しません。
新たに購入した住宅に対して、住宅ローン控除を適用すると、住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。例えば、ローン残高が3,000万円の場合、毎年30万円が最大10年間控除されます。
売却価格が2,000万円、取得費が3,000万円、譲渡費用が300万円の場合、譲渡損失は1,300万円(2,000万円 – 3,000万円 – 300万円)となります。この損失を他の所得と損益通算し、さらに控除しきれない部分を翌年以降3年間繰り越すことができます。
\ 税金ガイドBOOKプレゼント中 /


不動産にまつわる税金のことが一目で分かりやすく説明されている全110ページのガイドブックです(公益社団法人 埼玉県宅地建物取引協会発行)。弊社で無料査定して頂いて、売却されることが決まったお客様全員にプレゼントしています!
まとめ
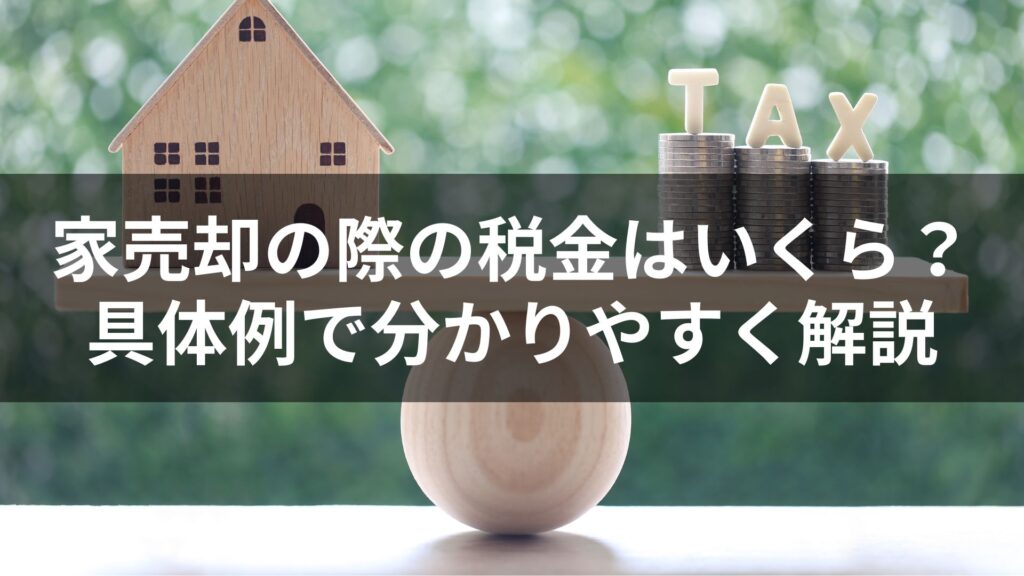
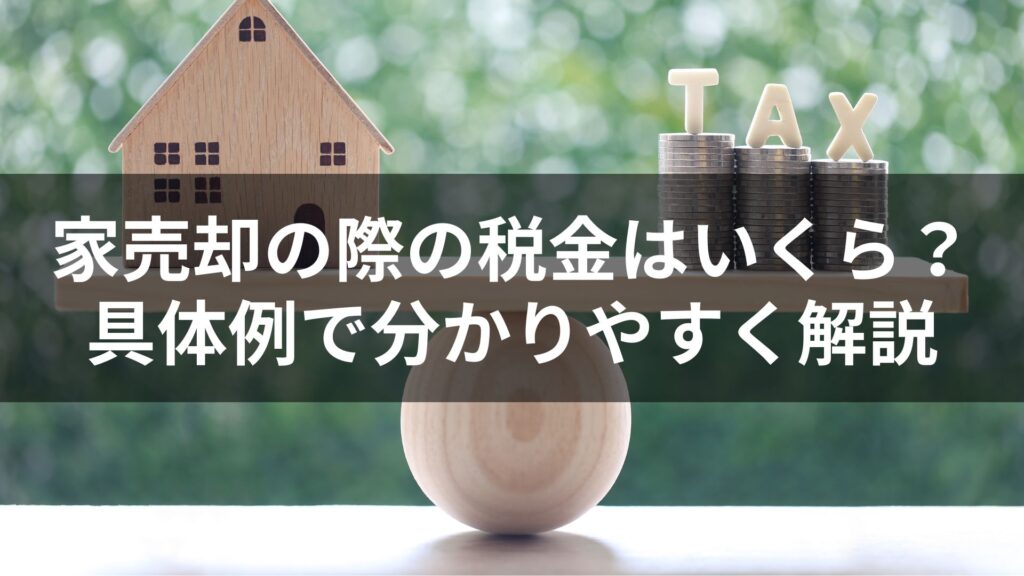
今回の記事では、家を売却する際にかかる税金や節税対策について詳しく解説しました。家を売る際の税金は、所有期間や売却価格、特例の利用状況によって大きく変わります。
以下に主要なポイントをまとめておきましょう。
- 家を売却する際には、印紙税や登録免許税、場合によっては譲渡所得税が発生します。
- 譲渡所得税は所有期間に応じて税率が異なり、5年以下では短期譲渡所得として39%、5年超では長期譲渡所得として20%が適用されます。
- 節税対策として、3,000万円の特別控除、住宅ローン控除、譲渡損失の特例、所有期間による軽減税率などが利用できます。
- 税金支払いのタイミングを把握し、確定申告を忘れずに行うことが重要です。
- 正確な税金計算のために、取得費や譲渡費用を正確に把握し、必要な書類を準備しましょう。
- シミュレーションを行い、最適な節税対策を検討することが、無駄な税負担を避ける鍵です。
家を売る際の税金については、専門的な知識が必要となるため、専門家に相談することをお勧めします。正確な情報を基に計画的に進めることで、税負担を軽減し、スムーズな売却を実現しましょう。
不動産売却時の税金や節税対策について理解を深め、適切な対策を講じることで、安心して家の売却を進めることができます。
\ 川越・所沢・狭山の不動産売却ならお任せ /
市街化調整区域の土地、相続を受けた遠方の不動産、事故物件、再建不可の建物など、他の不動産会社で買い取り不可と判断された不動産でも、弊社であれば買い取り可能な場合もあります。是非お問い合わせください!